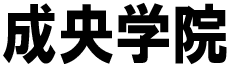2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月 2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月
令和7年10月21日(火)
講師の根木です。
最近はめっきり肌寒くなってきたので皆さん、体調管理にはより一層気配りしてください。特に受験生はこれから大切な時期となりますので。
さて今回の一言ですが、リスニングについてです。私ごとで恐縮ですが、家族が声楽をやっており、YouTubeなどで声楽家の演奏を一緒に聴く機会があります。個人的にはクラシックの素養も興味も全くありません。特に意識せずに他のことをやりながらBGMとして聴いてきました。
ところが最近、急に演奏が分かってきたようになった感じがして聴いたあとにその演奏について評価をするとなぜか10年以上声楽をやっている家族の評価と合致していることが多くびっくりしています。
これで、何が言いたいかというとリスニングの上達は耳が慣れるということに尽きるということ。
もちろん声楽と英語は違いますので単純に結論付けることは出来ませんが、実際に経験したことで感じたことを寄稿させて頂きました。
令和7年10月13日(月)
 こんにちは。
こんにちは。
小中学生担当の森谷です。
気候的に気持ちの良い季節がやってきました。生徒の皆さんは勉強も頑張りながら、どのような秋を楽しんでいますか?
私は、以前から行きたかった草間彌生さんの美術展に行く機会があり、芸術の秋を楽しみました。
草間さんの作品といえば、水玉模様やカボチャのオブジェが知られているかと思います。
それぞれの作品には題名だけが付けられていて、正直何を表現したいのかなと思う作品もあったのですが、途中学芸員さんがこう説明してくれたのです。
「草間さんの意向で、敢えて作品の説明は付けず展示しています。一人一人に想像しながら楽しんでもらいたいということです。」
なるほど〜!自分で考えて想像することで何倍も作品が楽しめるんだなと思いました。
今皆さんは塾に来た時どうしてもインプット型の勉強が多くなっているかと思います。それは知識や問題を解決する方法を教わり、身につけることがとても大切だからです。
そのあと、どれだけアウトプットして自分の考えを発したり、解決したりできるか。
例えば、好きな絵を見て想像力を膨らませて感じたことを表現したり、工夫してアイデアを出して新しい何かを考えだしたり…。
柔軟な考えのできる皆さんなら、行動に移すことで無限の力が発揮できることでしょう!
草間さんは90歳を超えた現在も精力的に創作活動を続けておられ、作品からは力強さや色々なメッセージが伝わってきます。
美術作品に詳しくない私でも充分に楽しめて、考えを深めることができました。
感性を磨いたり、リラックス効果も得られる美術鑑賞、お勧めです♪
令和7年10月9日(木)
こんにちは 小中学生担当の知名です。
暑い夏が終わり、清々しく外出したくなるような季節になりましたね。ということで私は先月末に世界遺産に登録されている岩手県平泉市に行ってきました。中3以上の皆さんは歴史、国語の授業で平泉について学んだことがあるかと思います。中2以下の皆さんは、これから学ぶことがありますので頭の片隅に入れておいてくれたら嬉しいです。実際に現地に行ってみると、感動したり、意外に思うことがありました。
皆さんも修学旅行や家族旅行でいろいろな場所に行くことがあると思います。そこで見たり聞いたりすることは、先人たちがどういう考えで行動していたのか、何を大切にしてきたのかを考えるきっかけになるのではと思います。もちろん受験生の皆さんは、今は旅どころではないでしよう。いつか時間ができた時は、是非いろいろな場所に行くことをお薦めします。今回は世界遺産として有名な平泉中尊寺、毛越寺以外の場所で「おくの細道」に出てくるところを辿って、私が感じたことをお伝えしたいと思います。
 まず右の写真は柳之御所遺跡です。藤原三代の御所だったと思われる場所です。
まず右の写真は柳之御所遺跡です。藤原三代の御所だったと思われる場所です。
松尾芭蕉の「おくの細道」に出てくる「三代の栄耀一睡のうちにして、大門の跡は一里こなたにあり。秀衡が跡は田野になりて、金鶏山のみ形を残す」とある場所です。御所の大門は高館から一里(4km)ほど手前にある。とのことですが実際に歩いてみると1kmも離れていなかったです。(Googleマップでも850m)
 また金鶏山のみ形を残す。とありますが左の写真の奥の林のような場所が金鶏山です。無量光院跡にあり、山というより丘。想像よりかなり低くて驚きました。金鶏山は自然の山ではなく、藤原氏が作った巨大な築山(庭園に作られる小高い土を盛ったもの)だったようです。
また金鶏山のみ形を残す。とありますが左の写真の奥の林のような場所が金鶏山です。無量光院跡にあり、山というより丘。想像よりかなり低くて驚きました。金鶏山は自然の山ではなく、藤原氏が作った巨大な築山(庭園に作られる小高い土を盛ったもの)だったようです。
「まづ高館に登れば、北上川、南部より流るる大河なり。衣川は和泉が城を巡りて、高館の下にて大河に落ち入る」
 ということで、先ず高館に登ってみました。6〜7分くらい登ると頂上にある高館義経堂(たかだちぎけいどう)に着きます。
ということで、先ず高館に登ってみました。6〜7分くらい登ると頂上にある高館義経堂(たかだちぎけいどう)に着きます。
右の写真奥のお堂のようなところです。源義経と妻子の居城で、命を落とした場所でもあります。どういう気持ちで義経は最期を迎えたのでしょうか。
 左の写真は北上川、そしてその手前の草原が『兵どもが夢のあと』と思われます。そこは今でも夏草に覆われていました。
左の写真は北上川、そしてその手前の草原が『兵どもが夢のあと』と思われます。そこは今でも夏草に覆われていました。
最後に金色堂のある中尊寺入り口で武蔵坊弁慶の墓を見つけました。弁慶は奥の細道には出てきませんが弁慶と源義経のお話は歌舞伎の勧進帳という演目にもなっています。弁慶のお墓の前で歌舞伎の「見得」のポーズを奉納してきました。
 皆さんも旅行などでいろいろな場所に行く機会があるかと思います。そこで何を思うか感じるかは人それぞれですが、良い経験ができることを願っています。
皆さんも旅行などでいろいろな場所に行く機会があるかと思います。そこで何を思うか感じるかは人それぞれですが、良い経験ができることを願っています。